第5章
1、
ロウソク岩は先端に火をともしながら、夜の海岸に立っていた。

闇の中に長方形の白い岩肌が異様にくっきりと浮かび上がっている。潮が引いているので、岩の土台の部分もほぼ完全に露呈している。
燃えているのは、岩の頂上に密集する松の木であるらしい。理由は分からないが、先端の松の木の部分が勢いよく燃え上がっていた。
打ち寄せる波の音が全身を包み込む。民喜は立ち上がり、岩に近づいてゆこうとした。もっと近くでこの不思議な光景を見てみたかった。それはまさに点火された巨大なロウソクそのものだった。
岩と民喜を隔てる距離は、およそ50メートルほど。銀色に輝く浅瀬が鏡のようにロウソク岩の姿を逆さに映し出している。
半分ほど歩いたところで、打ち寄せる波が裸足の足元を濡らした。ヒンヤリと冷たい。民喜はこれが夢ではないことを自らに言い聞かせた。
地震で失われたはずのロウソク岩が立っている――。
この状況は民喜の心を激しく揺り動かしていた。どうして先端の松の木が燃えているのかは不明だが、その姿自体に違和感はなかった。むしろこれがロウソク岩の本来の姿なのではないかとさえ思った。
勢いよく波間に足を踏み入れる。水面に写っているロウソク岩の像が揺らめく。民喜はジャブジャブとしぶきを立てながら、岩の方に近づいていった。
間近で見るロウソク岩は、思いのほか大きかった。先端の松の木の部分も含めると30メートル近くの高さがあるかもしれない。それは何か意志をもった巨大な石像のようにして民喜に向かい合っていた。緊張で背中の筋肉が硬くなってゆくのを感じる。民喜は深呼吸をした後、勢いをつけて土台の部分によじ上った。
立ち上がり、そそりたつ岸壁の表面に片手でそっと触れてみる。ゴツゴツとした岩の感触……。今度は両手を使って押してみる。堅く、どっしりとした、岩の感触。確かに、目の前にロウソク岩は存在していた。
「夢じゃねえ」
民喜は何度も自分にそう言い聞かせた。はるか上を見上げると、やはり先端の松の木は勢いよく燃え続けていた。
民喜は岩の壁面に手をかけたまま、しばらく松が燃える様子を眺めていた。しかし、松の木は一向に燃え尽きる様子はない。むしろ時間が経つほどに炎の勢いは増してゆくようだった。
「なしてあの松は燃え尽きねえんだろう」
民喜は不思議に思った。
よく見てみるとその燃え方には何か尋常ではないものがあった。松の木が燃えているというより、松の木に炎のようなものが宿って、光を放っていると表現した方が正確であるかもしれない。その証拠に、炎の熱気はこちらにはまったく伝わってこない。木から煙は生じておらず、炭も灰も一切落ちてはこない。
先端に密集する松の木はその姿形を変えないまま、不思議な光明に包まれ続けている。
民喜――
再び誰かに名前を呼ばれた気がした。はるか、上の方から。
民喜は思わず、
「はい」
と返事をした。
その声は、燃える松の木の間から発されているようだった。その呼び声は一人の声のようでもあり、また大勢の声のようでもあった。
すると民喜は目の前の岩肌に何か文字のようなものが刻まれていることに気が付いた。
それは日本語ではなく、どこか異国の古代文字のようだった。文字の一部がⅤ字形にとがっており、世界史の授業で習った楔形文字に少し似ていた。上からの光が文字に鋭い陰影を造り出している。よく見てみると、岩の壁一面に文字が記されていた。
民喜はここに書かれているのは何かの「法典」だと直感した。そう言えば、世界史で習ったハンムラビ法典も、ロウソクのようなかたちをした石柱に彫られていたっけ……。
岩肌に彫られた文字を、指先でそっとなぞってみる。自分には読めるはずのない太古の言語が、何故か判読可能であるものに思えた。それらの文字は、民喜に読まれることを求めていた。その内容を理解することが、岩の先端に宿る炎の願いであるように感じた。
文字をジッと見つめて、その意味を理解しようとしてみる。何か訳語が浮かんできそうな感覚があったが、あと少しのところで言葉はまた意識の底に沈んでいった。刻まれた文字を指でなぞりながら、民喜ははがゆさと焦りを感じ始めていた。ここにきっと、極めて重要な文言が記されているはずなのに。……
民喜はふと海の方へと視線を向けた。岩と自分を取り囲む漆黒の海はいつしか群青色に変化していた。水平線の上部には淡いオレンジ色が混じり始めている。
「もうすぐ朝が来るのか」
民喜は呟いた。
視線を少し上げると空に一点、明けの明星が瞬いていた。その瞬きは民喜の目に、とても意味深いもののように感じられた。……
ガクッ――
目の前の世界がずり落ちた感覚の後、民喜は目を開けた。
ゆっくりと顔を上げ、辺りを見回す。民喜は布団の上に座禅を組むような姿勢で座り込んでいた。
自分が夢を見ていたのか、それとも今見ているのが夢なのかよく分からず、暗い部屋の中でしばし茫然とする。耳にはいまだ波の音が残っている。足には波のヒンヤリとした感触が残っていて、手には岩のゴツゴツとした感触が残っている。
民喜は枕元にあるスマホを手に取って時刻を確かめた。
午前3時14分。
暗闇の中に青白く浮かび上がる画面を見つめながら、民喜はさきほどの不思議な光景を思い返した。
ロウソク岩の先端に宿るあの炎のようなもの――。それは民喜に対して岩の表面に刻まれた文字を理解するよう促していた。あともう少しで、文字の内容が読み解けそうであったのに……。
スマホを布団の上に置き、ジッと虚空を見つめていると、ふと、
《存在したものが……》
という言葉が浮かんだ。
《存在したものが、あたかも存在しなかったかのようにされてしまうことが、ないように。……》
この言葉は何だろう?
民喜は全身の神経を集中させ、どこかから浮上しようとしている言葉を聴き取ろうとした。
それは散文というより、むしろ短い詩のようだった。
急いでスマホを手に取り、メモ帳のアプリを開く。忘れない内にいま浮かび上がってきた言葉を画面に打ち込んでおこうと思う。
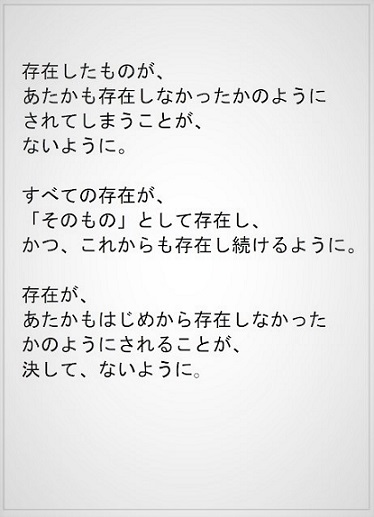
数分後、これらの文言が発光する画面の上に浮かび上がった。
存在したものが、
あたかも存在しなかったかのように
されてしまうことが、
ないように。
すべての存在が、
「そのもの」として存在し、
かつ、これからも存在し続けるように。
存在が、
あたかもはじめから存在しなかった
かのようにされることが、
決して、ないように。
初めて出会った言葉であったが、同時に、知っている言葉でもある気がした。ずっと昔から、自分がよく知っている言葉であるようにも感じた。
スマホに文字を打ち終えると突然、強烈な眠気が民喜を襲った。スマホを布団の脇に置き、ゴロンと横になる。
どこかから、波の音が聴こえてくる。砂浜に打ち寄せ、引いてゆく波の音……。
意識がまどろみ遠のいてゆく中、明けの明星が最後まで民喜の頭上で瞬いていた。
