2、
祖母の家に引っ越して一週間ほどが経ったとき、民喜は夢を見た。本体が失われて土台だけになったロウソク岩の上に一人で立っている夢だった。
どうやら満潮の時刻であるらしく、岩の周りを真っ暗な夜の海が取り囲んでいる。
(どうやって陸に戻ろうか)
そう思案していた民喜はふと、足元に薄い石の板のようなものが置いてあることに気が付いた。しゃがんで手に取ってみる。iPadくらいの大きさで、それほど重くはなかった。
石の表面をのぞき込んでいる内に、
(これはやはりタブレットなんだ)
と思う。板を左手の手の平に載せ、右手の人差し指で表面をスクロールしてみる。すると板全体がパッと青白く発光した。
(これはやはりタブレットなんだ)
光の中に何か文字が浮かび上がっている。横書きの、短い文章……。読もうとして目を凝らすが、すぐに文字のピントがぼやけてしまい、なかなか読むことができない。しかし、ここに自分にとって大切なことが書いてあることは分かっていた。……
翌朝、目を覚ました民喜はすぐにスマホを手に取った。画面を人差し指で素早くスクロールし、メモ帳のアプリを開く。すると、ロウソク岩の壁面から読み取ったあの「法典」の言葉が目に飛び込んできた。編集日時は8月19日と表示されている。
存在したものが、
あたかも存在しなかったかのようにされてしまうことが、
ないように。……
この言葉を忘れていたわけではなかったが、しばらく自分の意識から抜け落ちてしまっていた。これらの文言は改めて――まるで啓示のように民喜の胸を打った。
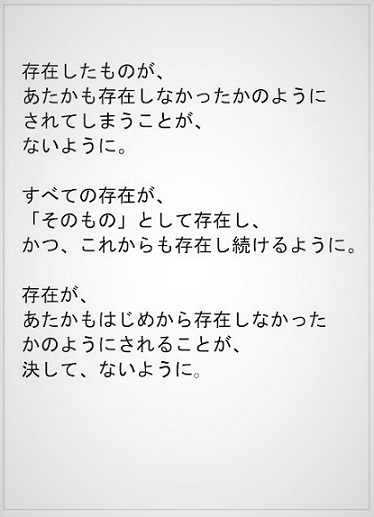
ジッと画面を見つめ、これらの言葉を胸の内で繰り返している内に、民喜の脳裏に故郷の風景がよみがえってきた。色鮮やかに次々と、音や匂いまでも伴って――。それは、事故が起きる前の懐かしい町の風景だった。
空を覆う真っ白な桜のトンネル。その下を楽しそうに行き交う人々。通りに並ぶたくさんの出店。母と手をつないで歩く咲喜。その様子をカメラで写す父。
駅のホームから見える満開のツツジ。線路沿いを彩る鮮やかな赤、白、ピンク。
毎日のように行っていたあの浜。ロウソク岩。打ち付ける波の音。潮の香り、駿と将人の笑い声。
6歳の時に初めて参加した火祭り。太鼓の音、大人たちの雄叫び。「頑張れー」と町の人の拍手と歓声に見送られ、上半身裸で自分の背丈よりも長い松明を担いで懸命に登った山道。
学校のグラウンドと校舎。教室での何気ない授業風景。
放課後の夕陽が差し込む美術室と、手にしみ込んだ油絵具の匂い。
実家のすぐ裏手にある雑木林。林にこもる植物と土の匂い。奥の方に生えるケヤキの樹。根本のあの洞……。
もう「戻らない」――
そう決めたあの町の風景が民喜の脳裏を駆け巡ってゆく。
存在したものが、
あたかも存在しなかったかのようにされてしまうことが、
ないように。……
スマホを手に、民喜は思わず立ち上がった。
最後に、満開の桜が咲く中、カメラを撮る父の姿が再び浮かんできた。
「民喜」――
父はカメラを手に、自分の名を呼んで微笑んだ。
父と目が合う。民喜の目から一筋、涙が流れ落ちた。
もう一度、故郷を訪ねなければならない。
布団の上に立ち尽くしながら、民喜はそう決意していた。
翌日、駿から電話がかかってきた。気分転換に一泊二日の温泉旅行に行かないか、という誘いだった。
「将人と話しててさ。来週の火水。直前の誘いで申し訳ねえけども」
「ありがとう、ぜひ。どの辺り?」
「いま、関東付近の温泉を探してて。祝日で混んでるかな、とも思ったけど。群馬の水上温泉っていうところで、ちょうど一部屋空いてる旅館があったんだ」
駿と将人と三人で温泉旅行。とても楽しそうだった。その予定でお願いしようと思ったとき、カメラを手にした父の姿が胸の内に浮かんだ。
「あっ……。旅館って、もう予約しちゃった?」
「いや。民喜の返事さ聞いてから、予約するつもりだった。まだ予約はしてねえ」
民喜は数秒の沈黙の後、
「せっかく調べてもらって申し訳ねえけど、別のところでもいいかな?」
「ああ、いいよ。他にどっか希望ある?」
「福島の……」
「ん?」
「浜通りの方で、どっかあるかな」
「浜通り?」
駿は幾分戸惑った声で聞き返した。
「んだ。あの、実はさ、ちょうど駿と将人に連絡しようと思ってたんだけど……。三人で久しぶりに、地元に帰りたいと思ってたんだ」
「地元に?」
「んだ。駿と将人と一緒に行ってみたい」
「うーん……まあ、いいけども」
「すまねえ。それでお願いしていい? どうしても、行きたいんだ」
思えば、自分の希望を強く主張することをしたのも、ずいぶんと久しぶりのことだった。民喜の口調に何かを感じ取ったのか、
「オーケー、分かった」
駿はすぐに了承してくれた。
「日常から離れた方が民喜の気分転換になるかな、と思ったけど。まあ、いいや。俺もしばらく帰ってねえしな。温泉も、浜通りの方で探してみる。将人にも伝えとく」
「すまねえ。勝手言って」
「いやいや、全然大丈夫。民喜が行きたいとこさ行こう」
次の日、将人からも電話があった。温泉旅行に山口凌空も誘っていいか、との確認の電話だった。
「来週、民喜たちと福島に行くってラインしたら、一緒に行きたいって」
病院で会って以来、将人は山口と連絡を取り合っているらしかった。
「ちょうど、一度福島に行ってみたいって思ってたらしく。もちろん、いいだろ?」
将人は民喜が了承するのが当然のような口調で訊いてきた。
「うん、まあ」
本当は三人で故郷を訪ねたかったのだが、「駄目だ」というのも変なので、了承する。どうやら将人は、山口凌空が民喜の東京での一番の友人だと思っているらしかった。
いや、しかし――確かにいま、山口が東京で最も親しい友人なのかもしれない。退院後、毎日のように山口はラインを送ってきてくれている。ちょっと強引なところもあるけれど、思いやりのあるいいヤツなのかもしれない。
そう思い直しつつ民喜は電話を切った。
11月1日、母と咲喜が浜松の祖母の家に引っ越してきた。
「お兄ちゃん」
玄関先に立つ妹を見て、ハッとする。あれだけ長かった髪の毛がすっかり短くなっていた。
「咲喜、髪切ったのか」
「うん! 切ったよ」
咲喜はニコッと笑って民喜の目を見つめた。
「お兄ちゃん、体調大丈夫?」
「ああ。咲喜も元気だったか」
「うん」
妹は手荷物を玄関に置いて、勢いよく手を挙げた。民喜も片手を挙げる。パチンとハイタッチをすると、妹はホッとしたような表情を浮かべた。
「髪を寄付するの……あの、何だっけ」
「ヘアドネーション」
「そうだ、ヘアドネーション」
「無事に寄付できたよ」
「そっか、よかった」
「あらー、咲喜ちゃん、大きくなったわねえ」
出迎えた祖母は妹を見て驚いたような声を出した。祖母が言う通り、確かにここ数か月で咲喜は急に背丈が伸びた気がする。
咲喜は微笑んで、
「お祖母ちゃん、これから、お世話になります。よろしくお願いします」
礼儀正しく頭を下げた。
「あら、ご丁寧に。こちらこそ宜しくね。お祖母ちゃん、咲喜ちゃんが来てくれるのを楽しみに待ってたのよ」
トランクを持った母が玄関に入ってきた。
「民喜、元気だった?」
「うん」
母は民喜の顔をジッと見つめ、頷いた。そして祖母の方を向いて、
「お母さん、ごめんね。これから、三人でお世話になります」
頭を下げる母を見て、民喜も一緒に頭を下げた。
「いえいえ、こちらこそ。さあさあ、上がって」
「お邪魔しまーす」
母が持つトランクを受け取る。
「咲喜、遂に髪切ったんだ」
「うん、そうよ」
母はニッコリ微笑んだ。
「ショートも似合ってるわよ」
祖母がスリッパを履く咲喜に声をかける。
妹はショートヘアにして、ずいぶんと印象が変わっていた。心なしか、大人びた雰囲気になっている。11歳という年齢を言っても、もう誰も意外に思わないかもしれない。
「これからはショートにするのか」
と尋ねると、
「ううん、また貞子ができるまで伸ばす」
咲喜はそう言ってウフフと笑った。
「貞子! じゃ、また何年も伸ばすのか」
「うん、3年か4年くらい」
「へー。偉いな、咲喜は。ちゃんと先のこと考えてて」
リビングに向かう妹の後姿を見つめながら、
(偉いな、咲喜は……)
民喜は再び胸の内で呟いた。
祖母と母と妹との、新しい生活が始まった。福島に残る父を除いての――。
